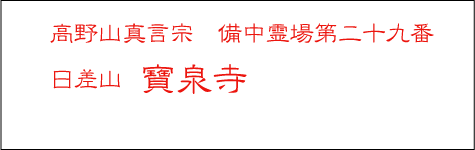
倉敷市から岡山市に向かう旧国道2号線の備中庄交差点から北へ向かって約3キロ程直進すると、桃太郎伝説で有名な鯉食神社がある。その西隣が日差山寶泉寺である。備前四十八ヶ寺を建立したことで知られる奈良時代の高僧・報恩大師(延暦14年6月28日 児嶋寺にて遷化)作の聖観世音菩薩を本尊としている。
この本尊は、今は天台宗である岡山・金山寺の千手観音、京都・清水寺(報恩大師の弟子・延鎮禅師創建)の聖観世音菩薩と並び「同木異躰の三観音」として信仰を集めている。
同寺は天平勝宝元年(749)、孝謙天皇の勅命によって報恩大師が建立した古刹である。大師は備中の日差山に上り一宇を建立し弟子に付属した。これが寶泉寺の始まりである。
この弟子を「知久」(室町時代作・金山寺縁起にも有り)と称し、桓武天皇の代には、桓武帝の眼の病いに勅使を立てて詔令を下し召されて見事に開眼。その功によって「心浄大師」の大師号を下賜されている。以後、日差山にて遷化、大師廟が現在も残されている。同寺縁起によると、日差山は観音堂、薬師堂、毘沙門堂、鐘楼堂、仁王門、鎮守杜、その他諸神勧請の霊場であったと記されている。
しかし、天正10年(1582)、織田信長・備中高松城水攻めの時は毛利・小早川隆景の陣所となったことから荒廃し、また慶長年間(1596~1615)の火災では本堂が灰燼に帰すれども、本尊は運び出し無事であったとある。当時は山内に12ヵ寺あったが、荒廃し2ヵ寺となり、寶泉寺だけが残ったとある。
ところで、現在の寶泉寺に安置されている同木異躰の観音菩薩像は、寛永13年から延宝6年(1678)の間、二度に亘って災難に遭いながらも難を逃れ、寶泉寺に還座するという逸話(池田光政公寄進の宮殿と脇仏)を残している。
現在は17年に一度のご開帳で、平成三年に開帳法要が厳修され、文化元年(1804)作の版木から本尊御影が配られ多くの人々と縁を結んだ。
日差山から現在の場所に寶泉寺が中興されるのは、『吉備国史』の記録から推察すると、延宝2年(1674)以降のようである。中興は宥泉法印となっている。つまり、本尊の観音像は日差山から二度の法難を受けるが、最後に還座する延宝6年には、現在の寶泉寺が中興されていたことになる。因みに、江戸中期、池田藩から石高二十石を受けていたと記されている。ともあれ、同寺は報恩大師作の「同木異躰の観音」を本尊として、そのあらたかな霊験と、地元民の篤い観音信仰によって、今日にその法燈を受け継いでいる古刹である。
●御詠歌 のどかなる春の日さしの山高み 明らけき世の始とうしる
●主な行事
正月修正会 1月18日初観音・大般若祈祷会 3月彼岸戦没者慰霊祭 6月青葉まつり(三宝会) 7月写経会 8月17日施餓鬼法要・子供盆踊り 9月彼岸戦没者慰霊祭 12月大晦日除夜会