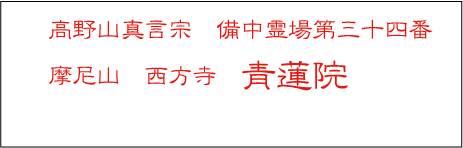
干拓史と共に栄え、弥陀信仰を現代に
現在の倉敷市はその昔、高梁川のデルタ地帯であり、数度におよぶ干拓によって平野部が築かれ町並みが整っていった。寺院も例外ではなく、栄枯盛衰を重ねながらも地元民の篤い信仰に支えながら現代にその法燈を伝えている。摩尼山西方寺青蓮院もその一つである。かつては戎市「白楽(ばくろ)市」が開かれていた干拓地に移転し、地元民と共に現代に信仰を受け継いできている。
現在の倉敷市の干拓は天正年間(1573~92)に行なわれており、それまでの倉敷市は高梁川の河口で船が盛んに往来していたという。青蓮院の前身である「安楽寺」は、現在の笹沖にあった葦高宮の別当寺院である。葦高宮は「帆下げの宮」と呼ばれたほどで、それほど流れが激しかったようだ。
『都窪郡史』によると、「摩尼山西方寺青蓮院は大高村大字白楽市字市場にあり、真言宗 西阿知遍照院末 本尊阿弥陀如来、本堂梁行三間半、客殿あり、開山智空上人、開基年月不詳 昔笹沖葦高宮の別当にして安楽寺と云ふ、寛文年中備前領分神道となりてより今は井上氏祠官となれり」とある。
和田住職によると「白楽市の干拓が元和年間(1615~24)だからその後ということになるでしょう」と話す。寺伝によると、寛文年間(1661~73)秀山法印によって現在地に移転され、同法印を中興開山としている。本堂は宝永2年(1705)に建立。客殿と庫裡は天保3年(1832)、第12世大雅の代に建立されている。
現在の青蓮院は住宅街の中に山門、鐘楼、礼拝堂「光明閣」(本堂の外陣に相当)、本堂、客殿、庫裡と並び、端正な佇まいを見せている。境内には不動明王と十三仏の石仏が建立されており、これは和田住職が堂内に入らなくても気軽に参拝できるようにとの配慮から建立したものである。
本尊は弥陀三尊で、文化財には指定されていないが、慈悲深い尊容をしている。特に阿弥陀如来坐像は寺名の通り、青い蓮の上に座しており、人々の信仰を集め、今日にその法燈を受け継いでいる。
御詠歌 ことごとく すくひまさむのこころより かぎりもしらぬ いのちなるらむ
主な行事
1月21日初大師 3月彼岸会 8月15日精霊送り・施餓鬼法要 9月彼岸会 毎月5日写経会 毎月21日本尊供