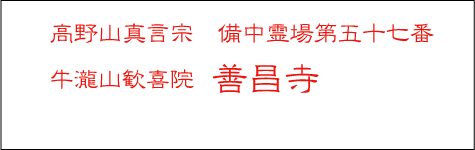
東寺の仏師 志水民部作の阿弥陀如来
JR山陽新幹線新倉敷駅の北口から北東へ約一.五キロ、山陽自動車道玉島インタ-から南へ約五百メ-トル離れた丘の上に (案内図)
牛瀧山歓喜院善昌寺がある。交通の便にとても恵まれ、又同寺から眺望できる水島、倉敷の景観は誠に素晴らしいものである。
広い境内の北手に聳える大きな本堂は庫裡客殿が一体となった横に長い建物になっており、屋根の大棟に施された龍の彫り
彫刻は素晴らしいものである。また、向拝に吊り下げられている寺号の書かれた提灯が印象的である。
善昌寺は、理源大師聖宝の開祖にして、寛永年間(1624-44)の頃の建立といわれている。
元禄年間(1688-1704)の頃に寺院として認められ金剛寺と寺号公称し、享保9年(1724)に院号が下賜され歓喜院と称している。
本尊の阿弥陀如来は、京都東寺の木仏師・志水民部の作であり、脇には弘法大師像も安置されている。
本堂の西側には地蔵堂がある。中には、享保16年(1731)讃州松尾の松井文左衛門富啓によって寄進されたと伝えられる千体地蔵尊が祀られている。明治24年に尊体彩色並びに堂宇修理が行われ現在に至っている。
善昌寺という寺号は伝えられている一説によると、同寺が寛永12年(1635)に田辺出雲守義昌の孫某によって開基創建され、「義昌」のい諱にちなんで「善昌」と名付けられたとのことである。 境内南側には山門があり、その下には長い石段の参道が続いているが、その山門のすぐ下には、狩野住職が園長を務める社会福祉法人 慈明会こばと保育園がある。この保育園は昭和26年に
「済世利人の真精神に立脚し地域社会の福祉増進をはかり、乳幼児が心身共に健やかに育成され正しい人格のもとが作りあげられるように」との願いで設立され、現在60人の園児達が、阿弥陀さんとお大師様のもと元気にすくすくと育てられている。
第五十七番 牛瀧山歓喜院 善昌寺
御詠歌 乃をもすぎ やまじにむかう あめのそら よしみね よりも はるるゆうだち