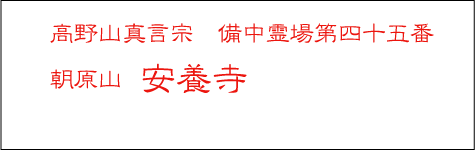
第45番 朝原山 安養寺
住職 小畑徹真
〒710-0007 倉敷市浅原1573 086-422-1110 案内図
本尊 金銅阿弥陀如来 開基 奈良時代 報恩大師
開山 正暦元年 源信僧都 中興 寛文12年
一千年の祈りを、今に伝える毘沙門天像群
倉敷市の奥座敷とされる倉敷市浅原に朝原山安養寺がある。倉敷市街の北約4キロの地、福山南麓に甍を垂れる同寺は毘沙門天本山と呼ばれ、毘沙門天信仰を一堂に集める古刹である。平安末期には百八体の毘沙門天建立が発願されており、千年の時を経てその祈りが伝わってくる。
同寺は奈良時代、報恩大師が国家祈願の寺として開山。11世紀には同寺一帯の「朝原寺」と総称する大伽藍が築かれ、なかでもその中心だった安養寺は正暦元年(990)、恵心僧都源信によって開山された。『源平盛衰記』には平安時代の末期、平家打倒の密謀が表になり、備前に配流された藤原成親が出家した記録が残されている。また、日本臨済禅を開いた岡山出身の栄西禅師も幼少のころ、この安養寺と関係があり、吉備真備以来、吉備王国が輩出した文化人、宗教家らの拠点として大きな影響を与えた寺院である。
現在、同寺には平安時代の毘沙門天立像42体(国重文)が残されている。この毘沙門天群はおよそ1200年前、桓武天皇によって祭祀され、鳥羽上皇が百八体の毘沙門天を祀ったとされており、同寺が毘沙門天の総本山とされる所以である。なかでも兜跋毘沙門天立像は、シルクロードのトルファンにその起源をもつ貴重なもので、仏教東漸の証人として現代のその姿を保っている。
このほか、同寺には国重文の木造吉祥天立像(平安期)や県重文の金銅阿弥陀如来立像(同)、同寺裏山の経塚から出土した銅造釈迦誕生仏(奈良期)や経瓦208枚、図像瓦5枚など出土品が保存されており、平安期を中心とした文化財の宝庫であると共に、その信仰を現代に伝えている。
同寺の山門の上には、高さ8m、三千貫という巨大な大毘沙門天福神像が建立されている。そして、世紀末の終わりと21世紀の始まりを告げる三千貫の大梵鐘がその姿を現わしている。これは、末法思想が広がった11世紀末の平安末期に百八体の毘沙門天建立の発願に意を体して、小畑住職が建立したものである。今、千年の祈りを経て、二十世紀末に毘沙門天信仰が甦ろうとしている。
●主な行事
1月1日~5日初詣開運祈願 2月旧暦初寅縁日初寅大祭(柴燈大護摩供)
4月8日甘茶まつり 11月3日(文化の日)毘沙門天秋季大祭
その他毎月1~3日月始め開運祈願 寅縁日参詣者祈願