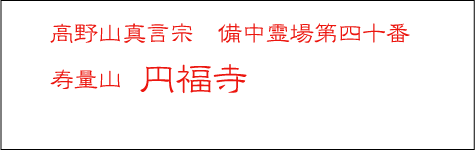
第四十番 寿量山 円福寺 案内図
鑑真和尚が創建、寂厳和尚が中興
JR山陽本線倉敷駅から国道429号線を西に約2キロ、国道から南に少し入った所に 寿量山 円福寺がある。円福寺の本尊は阿弥陀如来。仏師長助作である。
円福寺の開基は天平勝宝六年(754)。倉敷市北部の浅原山山頂に創建された。当時、浅原山山頂には鑑真和尚によって開かれた数ヶ寺の寺院があった。円福寺はその中の別当寺院として一山の中心を成していた。現在、その数ヶ寺の寺院は、神宮寺、井上寺、明王院、持宝院、福寿院、安楽坊となっている。
円福寺も応徳三年(1086)には、浅原山を離れて、大高村・葦高山の山腹に中興開基。現在の倉敷市笹沖(通称寺谷)にあった式内社葦高神社の塔頭寺院かつ別当寺院として、経覚阿闍梨を大願主に再建されたという。その後、延久二年(1070)には智空上人が円福寺に入住している。
現在地に移転中興したのは天文十一年(1542)。玉林玖大和尚の代に開始され、天正十四年(1586)宥誉上人の代に完成している。享保十四年(1729)には寂厳大和尚によって諸堂並びに、仏像、経典、仏画等の整備が行われている。
元治元年(1864)には、幕末動乱の影響を受け伽藍を大破。慶応元年(1865)に恵我阿闍梨が庫裡を新築し、明治十二年(1880)寿量慧日和尚が大願主となって市内東町にあった霊明山本堂を移転修築。昭和三年(1928)には、慈禅阿闍梨が「満州開教師」として当時の満州(中国東北部)に渡るのを記念して客殿を改築し、昭和五年(1930)には忠誓和尚の晋山を記念して、本堂改修が行われている。さらに、同九年に鐘楼堂、荒神社、その他を移転新設。中興第十九世豊成和尚によって昭和三十六年学舎新設、昭和五十一年本堂大改修され、平成十六年客殿を新築。
何れの建築も桃山時代の様式を模した雄大壮麗かつ貴重なもので、建築に携わった三宅備中守道晴氏棟梁一門の献身的協力と積極的技術革新による賜物である。
● 主な行事
1月 本尊講 2月 涅槃会 4月 釈迦降誕会花祭り 7月 荒神祭
8月 お盆 仏送り 地蔵盆 その他 春秋彼岸会
毎月 1日 16日 がお参りの日